反抗期の子どもと関わる
子育てで心が折れそうになるのは、反抗期の子どもの反抗的な態度ではないでしょうか。
私も若かりし頃は、反抗ばかりして親のいうことなど聞こうとしませんでした。
親の立場になると、いろいろな事が見えてきてありがたみも感じられますが、子どもの立場からするとタダタダ鬱陶しいばかりです。
以前の仕事でも、多くの反抗期真っ盛りの児童とたくさん関わってきました。
時には掴みかかられて、シャツが破けたことも何度かあります・・・( ´∀` )
そんなパワーが有り余る時期だからこそ、関わり方も慎重にしないと、どんどんこじれていってしまいます。

10歳を境にやってくる大きな心境の変化
私の経験上、3年生、7~9歳くらいまでは、まだまだ幼く大人の言うことも、素直に聞き入れてくれることがほとんどです。
ですが、だいたい4年生の夏をこえたあたりから、徐々に言動に変化が見られるようになってくる傾向があるなと思います。
ギャングエイジなどと言われますが、男子は数名のグループを作って大人の反応を試すかのごとく、ちょこちょこと悪さを繰り返し行います。
注意されたことに対しても、言い訳やふて腐れた態度をとる姿も見られるようになってきます。
この時に、(あぁこういう時期ですね)と心積もりあるのと、(あら、なんだか最近様子がおかしい。なんだかいつもの〇〇じゃない)ってとらえてあたふたするのでは、その後の関わり方も大きく変わってくるかと思います。

その時期にあった関わり方とは
反抗期でなんであれ、正す必要がある不適切な行動には指導する機会を設けます。
ですが、この時に(あぁこういう時期ですね)という前提があれば、間違っても頭ごなしに怒鳴ったり強制したりするカードは引きません。
なぜなら、これまでの関わりが無駄になるし、逆効果になるからです。
まさに火に油です。
指導者はあくまで冷静に、端的にどの行動が不適切なのか、これを続けるとどうなるのか。そして、どれくらい周りに迷惑をかけているかを理解してもらいます。
それでも改善が見られず、周りに危害が及ぶようだったら、厳しく、強制も必要かもしれませんが、まずは『冷静に関わる』カードを引くことが大切です。

とはいえ、親の立場なら、(あら、なんだか最近様子がおかしい。なんだかいつもの〇〇じゃない)
と動揺してしまうことは当然あるかと思います。
そして結果はだいたい、険悪な空気、ぎくしゃくした関係を作ってしまうことに終始しちゃうのではないでしょうか。
つらいですよね。
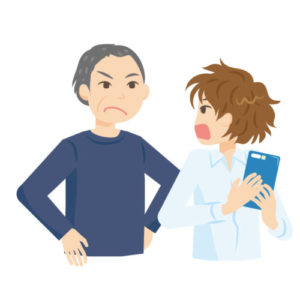
反抗期は悪いことではない
言うことを聞かない、反抗的な態度をとる時はとるもんだ、成長の過程だと、割り切ることも大切かと思います。
正直、物凄くイライラするときもありますし、爆発しそうなときもありますが。
ほぼ全ての人が通る道であり、そうやって自己を確立していくものですよね。
ついつい、目先のズレやほころびが気になってしまって、許せなくなって、すごく不安になってこのままじゃとんでもないことになるー!!
って、どんどん悩みの種がでかくなっていくんですけどね。
その一方的な心配がよけいこじらしちゃうことも多いです。
子どもとの衝突から学んだこと
昔、担任をもった6年生の児童の話です。
その子は常に反抗ばかりして、自分勝手で言うことも聞かないし、提出物もださない。
この子はこのままじゃ犯罪者にでもなってしまう!!
ってな勝手な心配を抱いて、毎日のように家庭訪問をしてたことがありました。

けれど、その子は卒業してから中学では部活に入り、真面目に活動するようになりました。
ある日、ふらっと僕に会いに来てくれて、敬語まで使えるようになっていました。
思わず目頭が熱くなりました。
それと同時に、子どもはちゃんとたくましく成長するって思いました。
その子には、「あの当時、先生が間違っていたよ。あれ以来、先生も指導の勉強しなおしてる」と伝えました。
自分の不安を映し出していませんか
ですが、ですがです。
反抗期だと受け入れて、それに合ったおおらかな関わりができれば、はなから苦労はしていないでしょう。
分かっちゃいるけど!!ですよね。
学級担任として、多くの児童と関わってきた経験から、正論や正攻法じゃどうにもならないときだってあるってことも分かるつもりです。
子どもは親を映す鏡
メンタルコーチとして活動を始めてから、多くの方の悩みを聴くなかで共通してみられることの一つに、
自分の悩みや過去の許せない感情、自分の親や世間の価値観を子どもに投影しているということがあります。
これは、過去の私にも言えることです。

客観的に、一歩引いて見てみればそこまで怒ることでもなかったり、こだわる必要もなかったりすることってないですか?
そない怒らんでも・・・みたいな。
これって、自分の内面を相手に映して見ているんですね。
鏡の法則と言ったりしますね。
相手の嫌いな一面は自分にもあてはまっているといいます。
自分自身のすべてにO.Kを出せていないからこそ、相手がそれをやっていたら腹立たしく思えてくる。
本当は、心の奥底では、やりたいと思っているのに。
子どもの頃、親が、周りが、環境がそれを許さなかったがために生き埋めにしてきた感情はありませんか?
あてはまることがあれば、ぜひ自分自身と向き合う時間も作ってみてください。
まとめ
反抗期の子育ては本当にしんどいと思います。心も骨も折れます。
子どもの成長の時期にあったコミュニケーションスキルで関わりが改善できる可能性は大いにあります。
そして、関わる側の心の持ちよう、現実の見え方次第でも、親子の関係は大きく変わってきます。
もし、あれもこれも試してはみたけどうまくいかない、
そもそも、そんな元気も気力もない、子育てに疲れてしまっている場合は第三者に頼る、コーチングを受けるなどしてみるのもよいかと思います。

